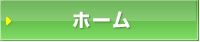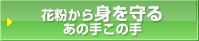花粉症は、花粉に対するアレルギー反応です。私たちの体には、体内に侵入しようとした細菌やウイルスなどの異物を排除する免疫システムが備わっています。体内に異物が入り込むと、免疫細胞は「抗体」という武器をつくり出して攻撃します。花粉症は人体にとって異物ではありますが、それほど害はありません。そのため通常なら花粉を攻撃することはなく、特に症状は現れません。
しかし花粉症の人の場合、免疫システムが過剰に反応して花粉に対する抗体が大量につくられます。するとアレルギー症状を引き起こすヒスタミンなどの物質が放出され、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみといった症状が現れるのです。
![]()
花粉に対する抗体がつくられるかどうかは体質によります。抗体がなければ花粉症にはなりませんし、抗体をもっているからといって、ただちに花粉症になるわけではありません。抗体は少しずつ体内に蓄積され、ある一定の量を超えると、ある日突然花粉症を発症するのです。
抗体がつくられる量には個人差はありますが、一般的に体内に入り込む花粉の量が多ければ多いほど、花粉症を発症しやすくなります。花粉症の人はもちろん、花粉症でない人も、花粉に接する機会をできるだけ少なくすることが大切です。詳しくは「花粉から身を守る あの手この手」![]() をご覧ください。
をご覧ください。

![]()
花粉症を引き起こす植物は、これまでにおよそ60種類が報告されています。代表的なのは春にみられるスギ花粉症で、花粉症全体の70%近くを占めると考えられています。これは、日本の国土に占めるスギ林の面積が12%と大きいことが影響しています。しかし、北海道や沖縄にはスギが少ないため、スギ花粉症の患者さんもほとんどいません。その代わり、北海道ではシラカバ花粉症が多いなど、日本国内でも地域によって特徴があります。
花粉症は原因となる花粉が飛ぶ時期にだけ症状が現れます。地域によって飛ぶ花粉の種類や時期が異なるので、いつ、どんな花粉が飛ぶのか知っておくと、対策に役立ちます。環境省の「花粉症環境保健マニュアル」![]() に花粉の種類と飛散状況が紹介されているので、参考にしてみてください。
に花粉の種類と飛散状況が紹介されているので、参考にしてみてください。
![]()
1998年の全国調査ではスギ花粉症の有病率は16.2%でしたが、2008年には26.5%に増加しています(*)。その背景として、第二次大戦後に盛んに植えられたスギの木が大きく成長したことに加え、温暖化により花粉の飛散量が増えたことが指摘されています。また、食生活の欧米化や住環境の変化などにより、アレルギー体質の人が増えたことも関係していると考えられています。
(*)馬場廣太郎ほか「鼻アレルギーの全国疫学調査2008(1998年との比較)―耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として―」