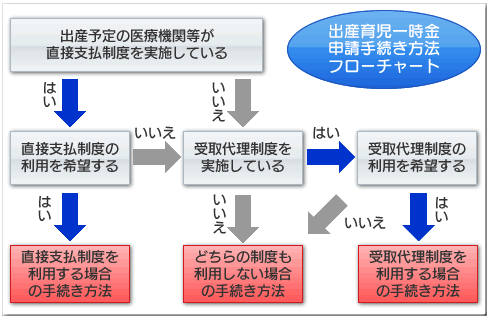出産費の補助として出産育児一時金を支給します

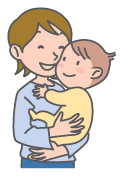
女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、1児につき42万円※が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。 ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、在胎週数第22週以降の出産(死産を含む、以下「加算対象出産」という)の場合。加算対象出産でない場合は40万4,000円。 |
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
被保険者等が出産予定の医療機関等と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します(契約は医療機関等で行います)。 出産育児一時金等の受取代理制度
小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。 この制度は、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出します。 *加算対象出産でない場合は404,000円 ※帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、「限度額適用認定証」により、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 >> 「限度額適用認定証 手続き」 ※海外での出産についてはどちらの制度も利用できません。 |
| 当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。 |
|
※直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金(420,000円*)は医療機関等に直接支払われるため、被保険者等には支払われません。 ※受取代理制度を利用した場合、「出産育児一時金(420,000円*)+付加金」は医療機関等に直接支払われるため、被保険者等には支払われません。 ※双児の場合は2人分となります。 *加算対象出産でない場合は404,000円 |
| 出産とは? | ||||||
 |
||||||
|
||||||
| 産科医療補償制度とは? | ||||||
 |
||||||
|
||||||
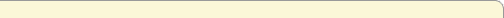 |
||||||||
|
||||||||